昨日の朝、国立競技場。
4時間前からワクテカ並んで、迎えた一戦。
開始7分に先制したときは狂喜乱舞だった。
その後のことは書かない。
さて。
不登校ジャーナリストの石井しこうさんの、
とてもわかりやすく温かい記事だった。
(タイトルはかなり「釣り」気味ですが)
連休明け、お子さんの不登校で
揺れている方はぜひ読んでみてほしい。
特にコレだなあと思ったところを
2つ、引用する。
親御さんとしては原因を取り除いてあげようと「学校へ行きたくない理由はなんなの?」「どうしたら行けるようになる?」と質問することも、同様にお子さんを追い詰めてしまいます。
お子さんは苦しいことがあって学校から離れざるを得なかったのです。その理由も、ほとんどのお子さんは言葉でうまく説明できません。
大人だって、何かから離れるとき、たとえば離婚や退職の理由を言葉にするのは難しいものです。お子さんも同じです。
いや、本当に!!!
親はつい、不登校の原因を探りたくなる。
僕もかつて散々息子に聞いてしまった。
でもたとえば離婚や退職の理由は?
確かに言葉にするのは難しい。
子どもも同じなんだよね。
そうやって心を寄せていくのが大事。
もうひとつ。
以前、「枕詞」がついてしまう、
という話を何度か紹介したけど、
まさにココなんだと思う。
不登校という状況に直面すると、親御さんはつい「この子は大丈夫だろうか?」と、色眼鏡で見てしまいがちです。
しかし、けっして忘れないでほしいのは、わが子はいつまでもわが子であり、不登校になる前もなった後も、その本質は何も変わっていないのです。
不登校という一面だけでお子さんを判断するのではなく、その子の持つ可能性や個性にも温かい目を向けてあげてください。
不登校という色眼鏡を外し、お子さんのありのままを受け止め、今、何が必要なのかを親として理解し努めること。その方針がしっかりと肚(はら)に落ちれば大丈夫です。
そうなのだ。
どうしても親は
「不登校になってしまった我が子」
という「枕詞」が頭の中に
点灯してしまうのだけれども。
この子はこの子。
不登校になる前もなった後も
本質は何も変わっていない。
そこをね。しっかりとね。
ありのままに受けとめる。
何度もいつでも繰り返し言ってますが。
そこがスタート地点なのでマイフレンド。
そこに立ればきっと大丈夫です。
今日も良い1日を。
P.S.
予約しただけでまだ手元に届いてないけど、絶対良い本だと思うので石井さんのこちらの新刊もぜひ。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!
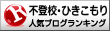







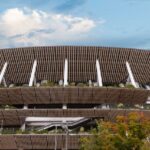













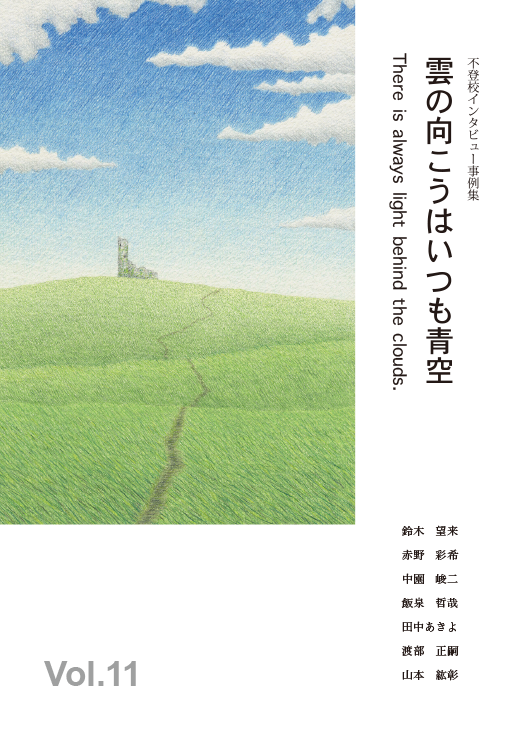










コメントを残す