前にも書いたことだけど、
僕が行った中学校の国語の授業はユニークで
三学期は中勘助の『銀の匙』の輪読だった。
中学生の時も良い小説だと思ったけど、
大人になって読み返すと実に味わい深い。
パラパラとこの本をめくっていたら、
目にとまったエピソードがあった。
中勘助が一番嫌いな教科だった修身。
孝行息子が殿様に褒美をもらうだの、
正直者が金持ちになるだの、
載っているのは味もそっけもない話ばかり。
子ども心にもとても納得いかない。
あるとき、彼はみんなが鵜呑みにしている
「孝行」について先生に質問した。
「先生、人はなぜ孝行をしなければならないんです」
先生は眼を丸くしたが
「おなかのへった時ごはんがたべられるのも、あんばいの悪い時お薬ののめるのも、みんなお父様やお母様のおかげです」
という。私
「でも僕はそんなに生きてたいとは思いません」
先生はいよいよまずい顔をして
「山よりも高く海よりも深いからです」
「でも僕はそんなこと知らない時のほうがよっぽど孝行でした」
先生はかっとして
「孝行のわかる人手をあげて」
といった。
中勘助が「ひょっとこめら」と書く
級友たちが一斉にぱっと手を挙げる。
私はくやしかったけれどそれなりひと言もいい得ず黙ってしまった。それから先生は常にこの有効な手段を用いてひとの質問の口を鎖したが、こちらはまたその屈辱を逃れるために修身のある日にはいつも学校を休んだ。
なんともはや。
苦笑を禁じ得ない話だ。
でも――、
とこの部分を読んでふと思った。
コレ、どっかの国の政治も、
なんか似てたりしないだろうか?
まっとうな質問に答えようとしない。
議論を避けて数の力をたのむ。
百年前のこの小説のエピソード。
なんだか同じところを回っている気がした。
週末は選挙です。
みなさんお忘れなく!

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!
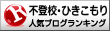

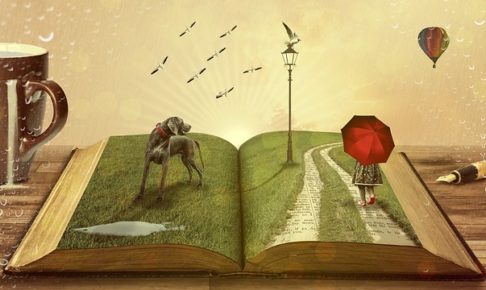


















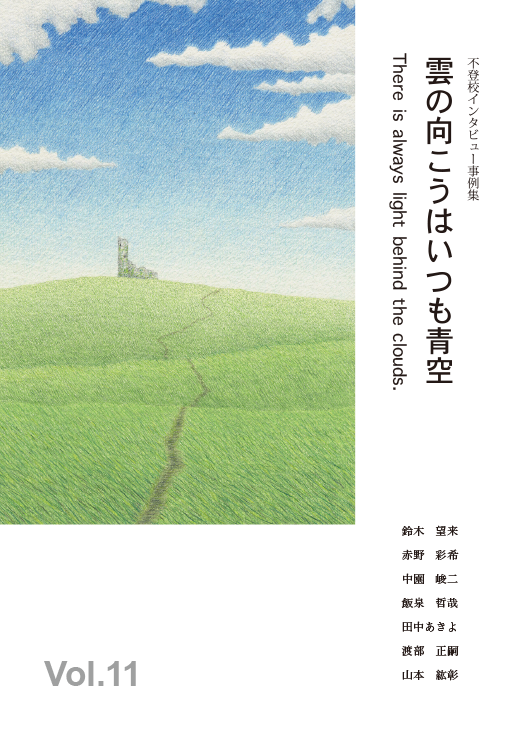










コメントを残す