よくよく考えてみたら、だけれども。
「不登校支援」
って変な言葉だよね。
「子どもが不登校になること」
それを「支援」する訳じゃない。
よね? もちろん。
でも字面だけ取ればそう読まれても
おかしくない言葉の構成だったりする。
本当、日本語って曖昧だ。
「じゃあ何を支援するの?」
ここが、実にフワッとしている。
以前「不登校の子を応援!」
という内容で発信されている方がいた。
読むとことごとく違和感しかない。
よくよく見れば元校長先生で、
子どもたちが元気に学校に戻ることを
心底応援したい、ということだった。
「そっちじゃないんだよね」
応援するべきなのは。
不登校支援とか不登校対策とか。
言葉はよく目にするようになった。
その実、方向性がよくわからない。
矢印がどっちに向いてるのか?
僕は息子が12年前に不登校になって、
7年前からこの活動を始めた。
「不登校10年選手」を自負してる。笑
今は自分なりの言い方がはっきりできる。
「不登校」を「支援」すること。
それは子どもを教室に戻すこと、
再登校を支援するんじゃない。
そうじゃない。
不登校で傷つく親子をサポートする。
不登校によってこうむる不利益を
最小限にするよう努めていく。
それが「不登校」の「支援」だと思う。
究極の目標は傷つく親子と
不利益をゼロにすること。
つまり学校は
行っても行かなくてもどっちでもいい。
そのことで傷つく親子もいない。
甘えだ、怠けだ、弱さだという
社会全体の偏見もなくしていく。
それが本当の意味での
不登校「支援」であって
不登校「対策」なんじゃーないのかな?
大きくて高い理想ではあるけれど。
不登校の子を減らそう、じゃない。
数の問題じゃないのだ。
不登校はどんどん増えて構わない。
不登校によって傷つく子を減らそう。
不登校で不利益を被る子を減らそう。
「減らすべき」を向ける矢印はそっちだ。
もちろん「結果としての再登校」
は全然ありだ。
多様化学校も含めてとにかく
選択肢はたくさんあった方がいい。
別に僕は学校を敵視している訳でもない。
ただ、ひとつ、力説したいことがある。
一番大切なことは――。
「子どもの意思」に反してまでも
「学校に戻ること」を上位目標に置いちゃ、
絶対にだめだということだ。
つまり嫌がってるのに戻そうとすること。
それは断固アウトだ、と言いたい。
これは子どもの人権の問題でもある。
昨日も書いたけど、ご存知ない方が
まだまだ多いと思うので繰り返し書く。
自死を選んだ不登校児のうち75%は
再登校していたという恐ろしい統計もある。
たかが学校、ではあるけれど、
されど学校、でもある。
取り返しのつかないことにもなりかねない。
支援や対策の矢印、お間違えないように。
そう思って偉そうに書いてみました。
うーん、我ながら偉そうだ。笑
今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!

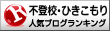









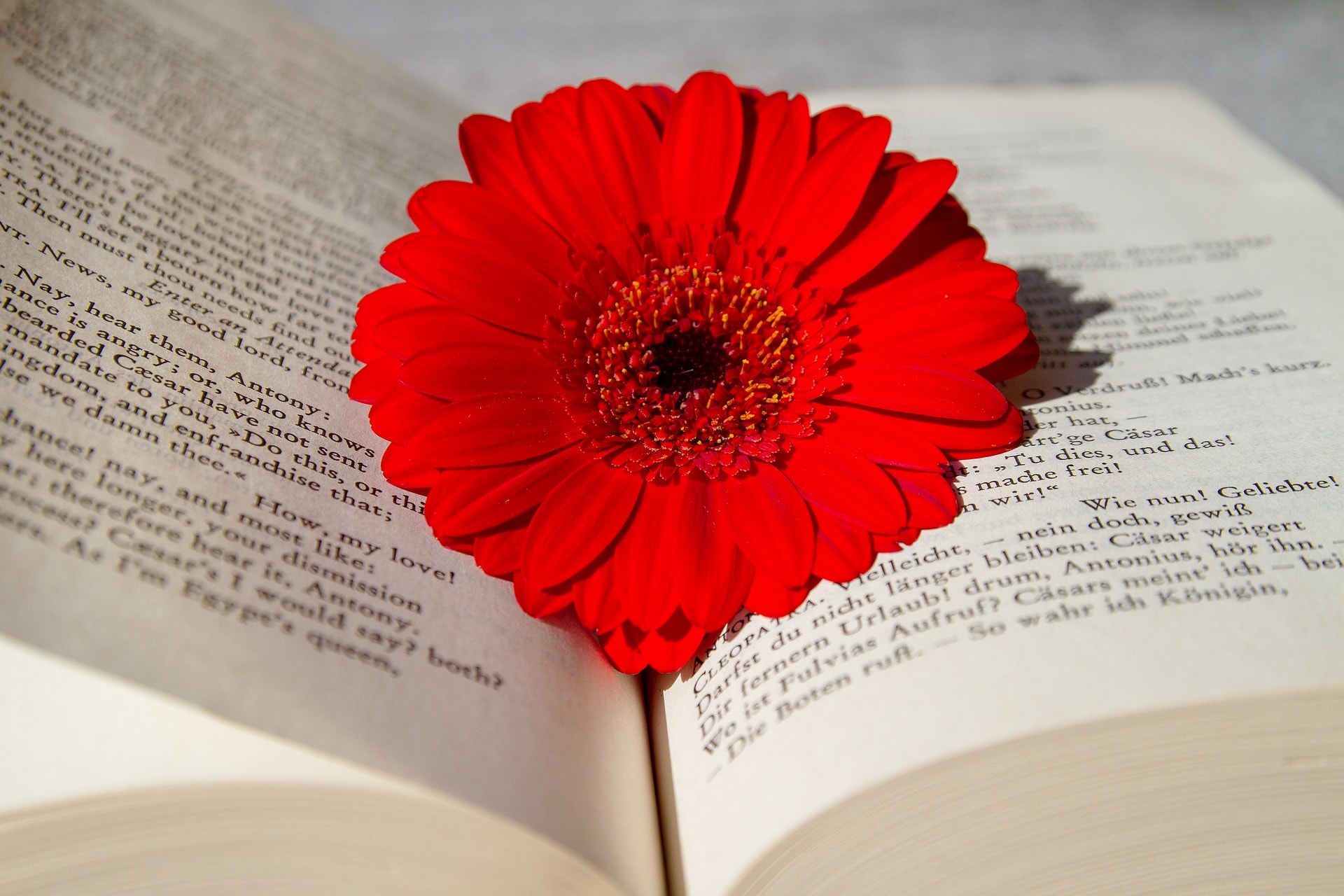







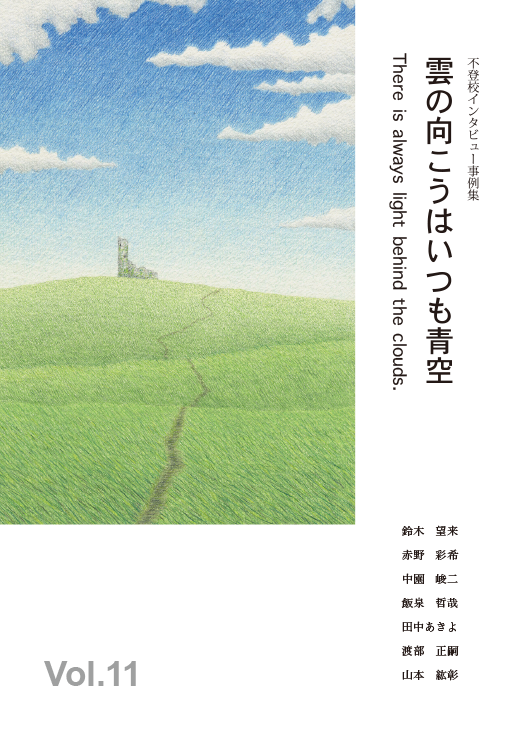










コメントを残す