このブログでも何度か紹介しているけれど、
広木克行先生の新刊が出たので読んだ。
広木先生のお話はもう多分
5回くらい実際にお聞きもしている。
毎度ながら素晴らしいのだけれども、
今回のこの本、すごく焦点がシンプルで、
かつ先生の思いがいつにもまして
強く溢れているように思った。
不登校とは、学校や家庭あるいは社会の有害要因(ストレッサー)に晒されてできる「心の傷」による苦痛の表れであり、その苦痛に耐えかねて「心の傷」を癒すために、今日の社会においては最後の拠り所である家庭に助けを求めている状態だということです。
タイトルにもあるこの
「心の傷」というキーワード。
これがもう、これでもかというくらいに
繰り返されているのがとても印象的だった。
不登校の子のこの
「心の傷」という本質を理解すること。
それなしには不登校からの回復はない。
この「心の傷」を理解していないから、
原因探しに汲々とする。
原因を取り除けば学校に行けるようになる、
と勘違いしてしまう。
だから「寄り添う」という
言葉の意味が理解できない。
「どうやったら学校に戻せるか」
から思考がスタートしてしまう。
もちろんかつて僕もそうだったから
このあたりの悩みはものすごくよくわかる。
だからこそ――。
僕が一番印象に残ったのは、
親の会に来ては、部屋の隅で黙って
何ヶ月も話を聞いているだけだった母親。
彼女が半年経って初めて
口を開いたこの言葉だった。
「私はここにきてからどうしたら子どもが学校に戻せるか、その方法を広木先生がいつ言うかと思ってずうっと座っていました。でも先生はこうすれば子どもは学校に戻りますよと一度も言わなかった。なんでだろう? と思って聞き続けていたら、やっとわかりました。不登校の子どもに関わるには、どうすれば学校に戻るかではなくて、まず子どもの苦しい気持ちを理解することが大事なのだと先生は話してこられたんですね。だから、あなたのお子さんはこんなことに苦しみを感じているのではないですか、ということを先生は一人ひとりの親の話を聞いてからずっと話し続けてきたのですね。それが初めてわかりました」と。
まさにね、ここが本当のスタートラインで。
ここに立つためにも、
子どもの最善の利益はなんなのか、
心の傷に寄り添うとはどういうことか。
親自身、真摯に向き合う必要がある。
それがすごく胸に染み入る本だった。
多くの人に届いてほしいと思います。
今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!
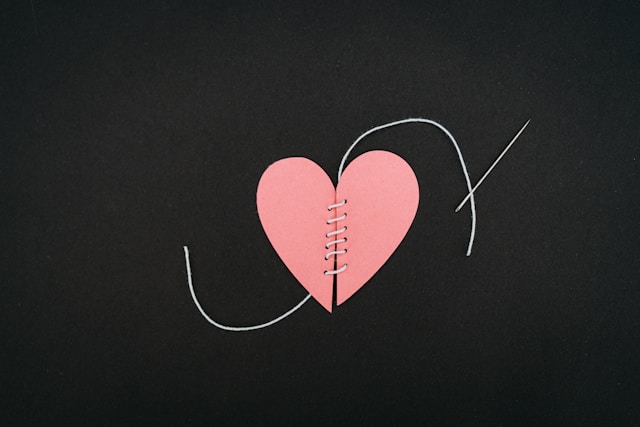


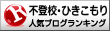
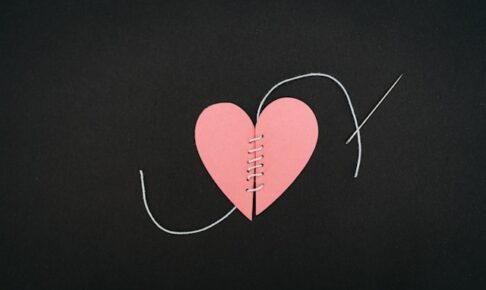
















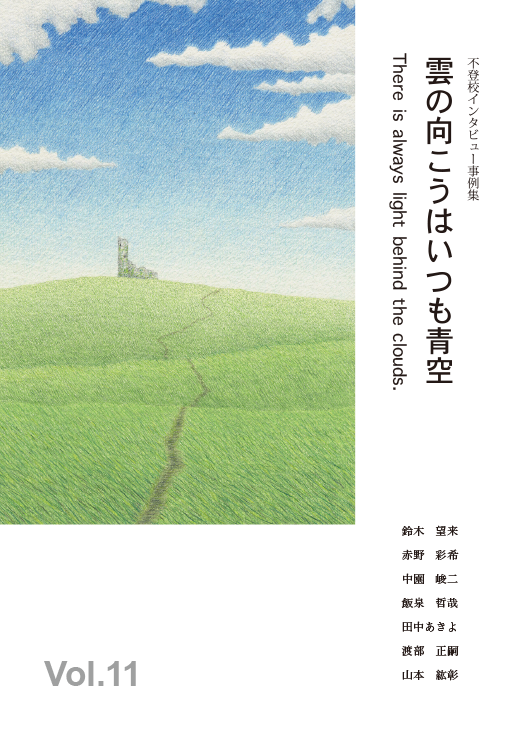










コメントを残す