江川紹子さんの「私たちも不登校だった」
という本を読んだ。
不登校を経験した8人を
ジャーナリストの江川さんが取材し、
そのストーリーをまとめたものだ。
2001年刊行の本で、そのぶん、
今読むとヒドイ話が多い。
乗馬に興味を示したところ、父親に
「北海道の牧場に連れてってやる」
と言われ、そのまま置き去りにされた
倉地透さんがその最たる例だけど、
登場するカウンセラーや先生たちは
ことごとく、普通に、
不登校は学校へ戻すことが前提だ。
親も力づくで学校へ行かそうとする。
そんなところには「時代」を感じた。
行けない理由は自分でもわからない
いじめがきっかけの人もいる一方で、
行けない理由が自分でもわからない、
という、こうした声も印象的だった。
「一度行けなくなると、もう先生がどうの、という問題じゃなくなるんですね。その空間への拒否反応と言ったらいいのか…。」(山谷千香さん)
「学校に行くか、行かないかという選択ではなかった。もう行くことができなかったんです」(鈴木祐司さん)
中でも僕が一番印象に残ったのは
梅沢しのぶさんの事例だった。
私は生きていてもいいんだ
真っ暗闇の海で、板切れ一枚に
つかまりながら、かろうじて
漂っている気がしていたしのぶさん。
それまでのカウンセラーも
しのぶさんの話は聞いてくれた。
でもひとしきり話し終わると、
彼らは必ず「でもね」と言ってきた。
間違いを正したり、違う視点を提示して
しのぶさんの気持ちを結局、
学校に向かわせようとする。
ところが、ある相談員は
「でもね」を言ってこなかった。
「そうだよね、そうだよね」
とひたすら聞いてくれた。
ひとしきりしのぶの話を聞いた相談員は、「そんなにしんどかったら、行かなくていいんじゃない?」と言った。
その瞬間、しのぶは狭いところに閉じ込められていた自分が解放され、目の前がパーッと晴れていくような気持ちがした。
(あー、私は生きていてもいいんだ)
決して大げさではなく、心の底からそう思えた。
聴くこと、そして目の前の相手を
まるごと受容することの大切さを
改めて感じる場面だった。
演じ続けた「不登校の優等生」
ただ、これでしのぶさんの
全てが好転するわけじゃない。
行ってみた不登校生たちの集まりも
決して楽園ではなかった。
そこでいじめにあった。
摂食障害にもなる。
「あの子は学校に行かないからこうなった」
と言われたくないあまり、
演じ続けた「不登校の優等生」。
自分らしく、自分らしく生きる、
であろうと頑張りすぎた――。
と、詳細は本を読んでいただくとして。
生きる力が育まれる過程
不登校生が何を感じ、
どんな思いでいたのか?
どういうきっかけで、何が変わり、
そしてその人の今があるのか?
それが丁寧に取材されている、
とても濃い一冊だった。
学校に行くか行かないかだけじゃない、
もっと大きな「生きる力」が
どう育まれていったか、その過程を
知ることができる良い本だと思う。
中古では手に入るようなので、
もしご興味あれば、是非。
今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!



















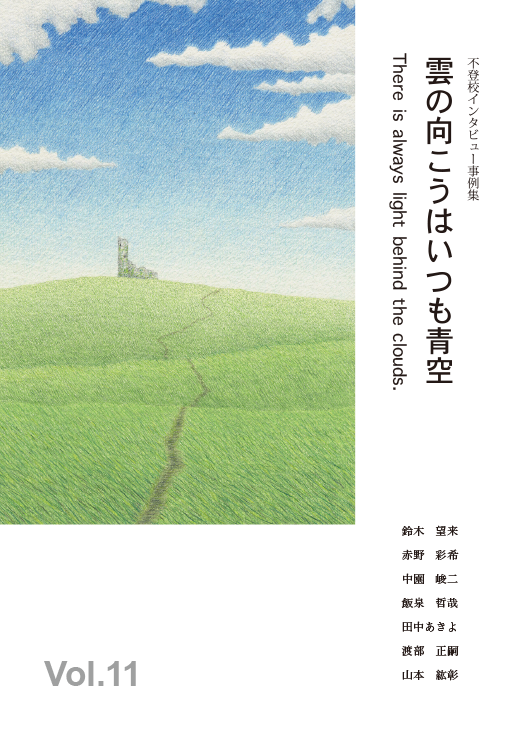










コメントを残す