「ああ、この本はぜひ、
学校の先生に全員読んでもらいたいな」
心からそう思った。
子どもたちはなぜ学校へいけないのか?
その背景にはどんな要因が隠れているのか?
その対応がわかりやすく書かれている。
そして論旨がものすごく明快だ。
最初に結論を言ってしまうと、発達障害の子が不登校になったときにもっとも重要なのは再登校してもかまわないけれども、「再登校は目標にすべきではない」です。30年以上の臨床経験を通じて、私はそのことを学びました。
子どもが不登校になったときに絶対やってはいけないこと。それは、親が子どもに「学校に行かない人はダメな人間だ」という価値観を見せることです。
例えば、子どもが学校を休む日が増えてきて、学校には行かないのにゲームはやりたがるという場合に、親が「学校に行くならゲームをやっていい」といった形で、取引のような話をすることがあります。これも絶対にやってはいけません。なぜかというと、それでは子どもに「学校に行かないあなたを、私はダメ人間だと思ってるよ」というメッセージを伝えることになるからです。
大人の側は、社会の荒波に耐えられるような強さを身につけてほしくて、あえて厳しい環境で頑張らせようとしているのかもしれませんが、それはムダな厳しさです。苦手なことを少しずつ身につけていけるようにサポートするのではなく、苦手だとわかっていることを無理にやらせて、ただ失敗させているだけです。
いや、本当にね。
普段思っていることだけれども。
ここまで明快にズバッと、
しかも繰り返し力強く仰ってもらえるとね。
読んでいて胸が熱くなる感じがあった。
そして話は冒頭に戻るのだけれども。
要するに親にできることは、
親子関係を良好に保つことで。
(遅くとも中3の夏休みまでには!)
本当に必要なのは、コレなんだよね。
学校の環境が子どもに合っていない場合には、子どもが頑張って登校して、一生懸命勉強しても、健やかな成長につながらない可能性が高いです。その場合に必要なのは、子どもが学校に行く努力をすることではなく、大人が子どもを理解して、環境を調整することです。
大人が子どもを理解する。
環境を調整する努力をする。
本当にここに尽きる。
そしてこの本ではその
「環境の調整の具体的な仕方」も
「これでもか」というくらい出てくる。
読めば読むほど、
子どもが変わるんじゃない、
学校が変わらなくちゃいけない。
そういう思いがどうしても出る。
そう、なんと言っても学校には
「ノルマとダメ出し」が多すぎるのだ。
そして子どもは学校もクラスも
担任も自分で選べない。
それを、僕ら親もまた、
どうすることもできない。
子どもと担任の先生の相性が合わない場合には、不登校の対応に「親の社会性」というか、「ある種の交渉力や政治力」のようなものが求められる場面があるかもしれません。
いや、本当にその通りで。
ある意味、12年前僕らの場合は
息子の学習障害のことでは
その交渉や政治をあきらめた。
だからこそね。
学校の先生にはぜひ読んでもらいたい。
もう教員免許取得に必須のバイブルとして、
全員に必読とレポート提出を課してほしい。
そう思うくらい、わかりやすく
具体的でいい本でした。
もちろん、親が読んでも良い本です。
でも読めば読むほど
「環境調整」には親だけではなく
学校側の理解と対応が必要だよなあと。
思っちゃう純ちゃんなんでした。
「二次障害の山を大きくさせない」
というワードもとても印象に残ったな。
何が言いたいか?
とりとめなくなっちゃったけど、
要するにひと言で言うなら――。
「先生、ぜひ読んでください!」
不登校のこと、めっちゃよくわかりますよ。
今日も良い一日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!


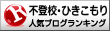

















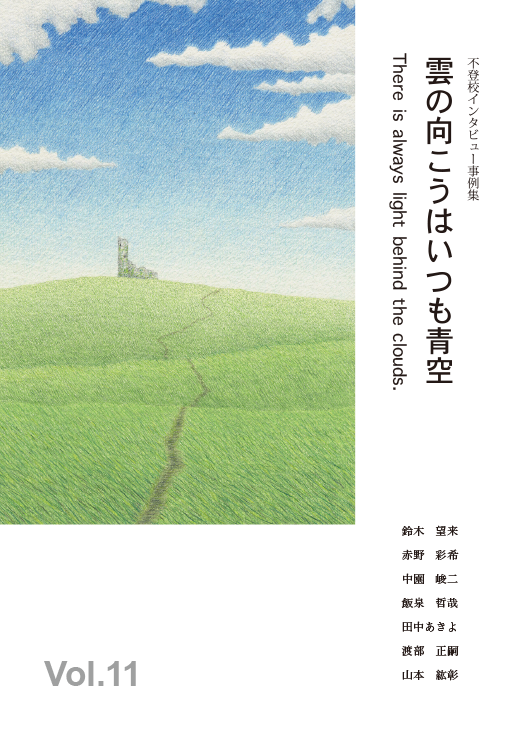










読みました!
巻末に学校とのコミュニケーションシートが付いていて、コピーして学校へ渡せるようになってる所も、痒いところに手が届く感じでよかったです。
不登校関係者の必読書として、先生や保護者に勧めまくっています。このサイトで取り上げていただき、とっても嬉しいです〜
かすたどんさん、コメントありがとうございます。
本当に読みやすいし、わかりやすくて、丁寧な本ですよね。たくさんの方に届いてほしいと思います。