「自分に矢印を向ける」
という言葉や言い方は、
少なくとも昭和にはなかったと思う。
「新しい景色を見にいこう」
もそうだけど、僕はサッカーの記事で
よく目にする印象がある。
それもここ5、6年くらいの感じかな?
率直にいい言葉だと思うし、
だからこそ流行っているのだろう。
って毎日サッカー記事ばっか読んでる。笑
そしてふと思ったのは――。
親も自分に矢印向けたほうがいいよね、
ということだ。
「どうしたらこの子は将来」
「なんとかしてこの子の自立を」
この場合の矢印は完全に
「私(親)→ 子どもの状態」
になっている。
問題は完全に「子どもの状態」の側にある。
そうではなく――。
一旦冷静にぐるっとひっくり返してみる。
「なぜ自分はこんなに心配なんだろう?」
と、矢印を逆に自分に向けてみる。
「子どもの状態 → 私(親)」
という投げかけだ。
なぜですか?
なぜそんなに不安なんですか?
ひと言で言うとその不安はなんですか?
それはあなたにどんな影響を及ぼしてますか?
この先、短期的、中期的、長期的に
どんな問題が起きると考えられますか?
って考えてないよね。
そんなこと掘り下げて考えたこともない。
いや、決して責めてるんじゃないんです。
僕も完全にそうだったから。
「どうしたらこの子が学校に戻れるか」
それしかずっと考えてなかった。
それを考えるのが親の役目だと思ってた。
「なんで自分はこの子に
学校に戻ってほしいと思うのか?」
「この子が学校に行かないことで感じる、
自分のこの不安の正体はなんなのか?」
「真に幸せな人生とはなんなのか?」
そんなこと、1ミリも考えやしなかった。
でも今にして思えば幸いなことに。
あれやこれやのドタバタもあり、
完全ににっちもさっちも行かなくなった。
そして田中茂樹先生の
『子どもを信じること』を読んだ。
そこで初めて矢印が自分に向いた。
いや、矢印を自分に向けるのは
苦しく、辛いことだ。
正直、この本を読むのは辛かった。
今までの価値観を問い直すことになった。
ある意味、自分の子育ての否定でもある。
でもね、何度も書いてるけど、
その過程なくして不登校の理解はない。
この苦しさをしっかり味わって
逃げずに向き合うこと。
厳しいけど、それが親にとっての
不登校のスタート地点だとも思う。
もちろん、行きつ戻りつだ。
何年も何年も時間がかかる。
なんせ僕は「10年選手」だから、
今はすっかりもうくぐり抜けて
偉そうにこうやって書いてるけど。
でもそうやって行きつ戻りつしていると、
なんとマア、不思議なことに!
「新しい景色」
って奴が、気づけば見えてたりする。笑
矢印自分に向けるのは苦しい。
一人じゃなかなか難しい話でもある。
だから、不登校の親の会だとか、
思いを同じくする人との繋がりが大事だ。
いろんな人の、いろんなケース、
いろんな思いや、価値観や体験談。
そこに触れていく中で、
「あっ」
「そうかも」
「確かに」
というような小さな気づきが
いくつも何度も繰り返し生まれていく。
そこから徐々に矢印が自分に向かい出す。
この活動をしていて思うのは、
やっぱりそういう場面が多いということだ。
なのでマイフレンド。
ぜひ繋がりを大事にしてください。
5月は25日にびーんずネットのホーム、
川崎でお散歩会もやるのでね。
よろしければ一緒におしゃべりしながら
朝の公園を歩いてみませんか?
参加費無料ですが、人数把握のために
お申し込みは必ずお願いします。
今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!
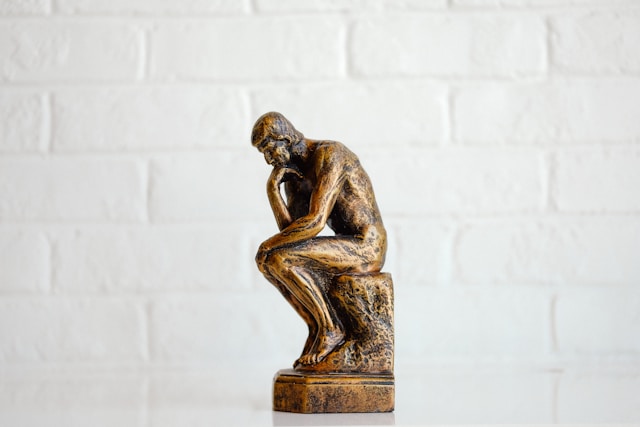

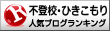
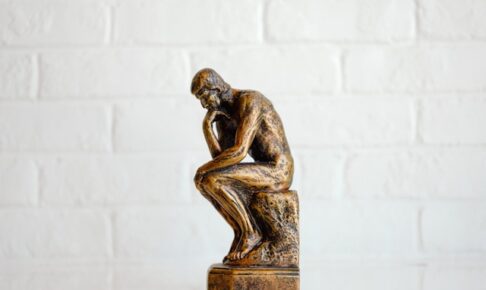
















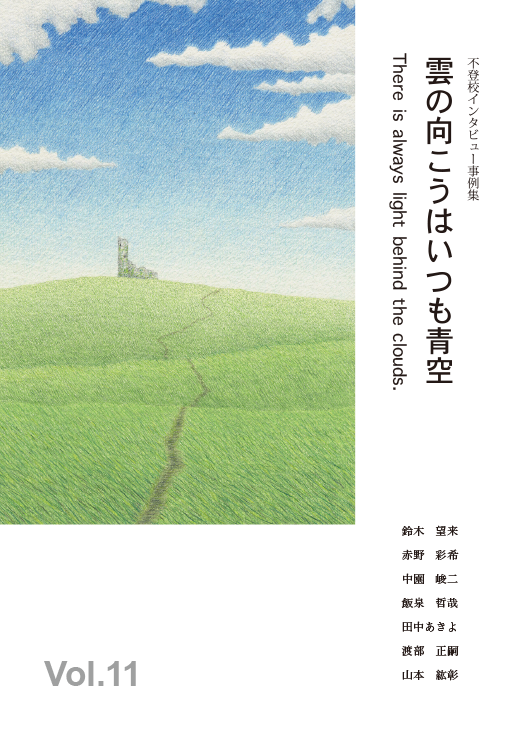










コメントを残す