子どもが不登校になる。
「親にできることはなんだろう?」
親ができることはたった3つだけしかない。
- 疲れている子どもを、これ以上疲れさせない
- 傷ついている子どもを、これ以上傷つけない
- 不安な子どもを、これ以上不安にさせない
今、僕は息子の不登校から10年以上経って
あれやこれやがあったからよくよくわかる。
本当にその3つだけだよね、と。
でも初期段階でとにかく慌てている人には
「そうは言っても……」となる話だろう。
「いつまで待てばいいのか?」
その不安を少しでも解消するためには、不登校の子どもがどういうプロセスをたどって回復していくのか、その「回復の地図」を持つことが大切だと思っています。そうすれば、「確かに今、このような状態だ」「ここまで回復しているのか」「今後起こるのはこういうことか」と現在地の確認ができますし、親子共に今後の見通しを持つこともできます。
まさにタイトル通り、
『不登校からの回復の地図』
がよくわかる本だった。
これ、本当に12年前に
息子が不登校になったときに読みたかった。
すごくわかりやすいし、
何より明快で勇気が持てる内容だから。
全編すごくよかったけど、
個人的に一番腑に落ちたのは122ページの
「子どもの心に寄り添うってどういうこと?」
の部分だった。引用する。
寄り添う親というのを「子どもの後をついていく親」と言った人もあります。
子どもが歩き始めたら同じペースで後をついていく。子どもが立ち止まったら、親も立ち止まる。そして歩き出すまで待つ。歩き出したら、また同じペースで後をついていく、ということです。子どもが右に行くと言ったら「分かったよ」とついていく。「左に行く」と言ったら「分かったよ」とついていく。
「やっぱり右に行く」と言ったら、「もういい加減にしなさい!」と言いたくなりますが、やっぱり「分かったよ」とついていく。先回りして無理やり「こっちに来なさい」と手を引っ張ることもなければ、後ろからどんどん背中を押して「早く行きなさい」とせかすこともない。子どもと同じペースでついていく。
しかし、本当に危ないところにいこうとするときには、きちんと止める、という親の姿です。
子どもの心に寄り添う親の姿、
とっても具体的じゃないですか?
要するに!
「いい加減にしなさい」
「こっちに来なさい」
「早く行きなさい」
それを言わない。
本当に危ないこと以外は口を出さない。
ただ親は「不登校」自体が
本当に危ないことだと思うから
つい、余計な口出しをするんだよね。
でもこの本を読めば、不登校は
「本当に危ないことじゃない」
と納得できると思います。
今日も良い一日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!


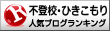

















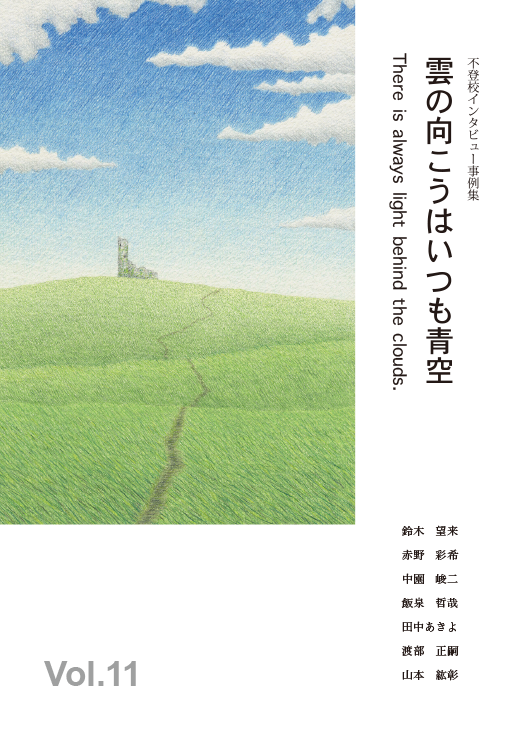










コメントを残す