個人的な思いを言えば、、、
「変な言葉だなあ」と思ってる。
「出席扱い」という言葉だ。
「何、それ?」
と思う。
「オマケで出席したことにしてやるゾ」
言うなればそんな、実に偉そうな
学校側からの上から目線さえ感じる。
なのでね。
あえて話題にしてなかったけれど。
「あ、こういうケースもあるんだな」と。
中学時代に不登校になった佐々木さんの生徒は、すららネットで学びを継続し、学校からも出席扱いとしてもらっていたそうです。その後、通信制高校進学後のテストで5教科ほぼ満点をとったといい、通学スタイルに復帰したそう。
佐々木さんは「学校という『本来結びつきたかったところ』から努力を認められたことで、自己肯定感の回復になったと思う」とし、「このような結果につながるなら、この仕組みを知ってもらう価値がある」と話します。
努力を認められたこと。
それが本人の自己肯定感の回復になった。
そういう意味ではこれもアリかもなあと。
ただね、力を込めて強調したいのは――。
「すららで勉強したから5教科ほぼ満点」
「通学スタイルに復帰した」
それはあくまでも二次的な副産物であって。
それを親が目論むのは違う。
もっかい書いちゃう。
それを親が目論むのは違う。
そういう下心で親が
子どもを動かそうとすること。
それには僕は断固反対です。
あくまでも大事なのは本人の意思だ。
本人が希望していること。
そして努力を認められたことが
本人の自己肯定感の回復になる。
――のであれば、やればいい。
そうでないなら
「出席扱い」なんて放っておけばいい。
放っておけばいいんだよ、出席扱いなんて。
何度もしつこく繰り返すけど、
あくまでも大事なのは本人の意思だ。
本人がやりたくないのに、親が安心したくて
(そう、親はいつも自分が安心したいのだ)
この出席扱いにやっきになる。
それは絶対に避けたほうがいい。
そして、一方で。
この仕組みのことを
6割の不登校の子どもが知らず、
9割の保護者が学校から説明を受けてない。
その現実もやっぱりあるのでね。
生徒の母親は「現場の先生を責めたいわけではない。現場が安心して運用できるような、明確なガイドラインや実例が必要だと思っている。制度がかたちだけでなく、生きたものになるようにしてほしい」と訴えます。
先生を責めたいわけじゃない。
ただ制度が生きたものであってほしい。
それにはまったく同感です。
「出席扱い? なんのこと?」
という方はぜひ全文を。
(ただし下心で目論まないでください)
今日も良い一日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!

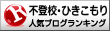




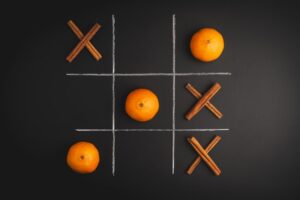




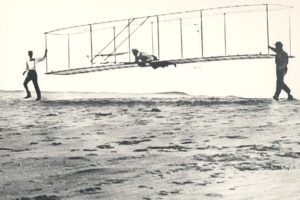







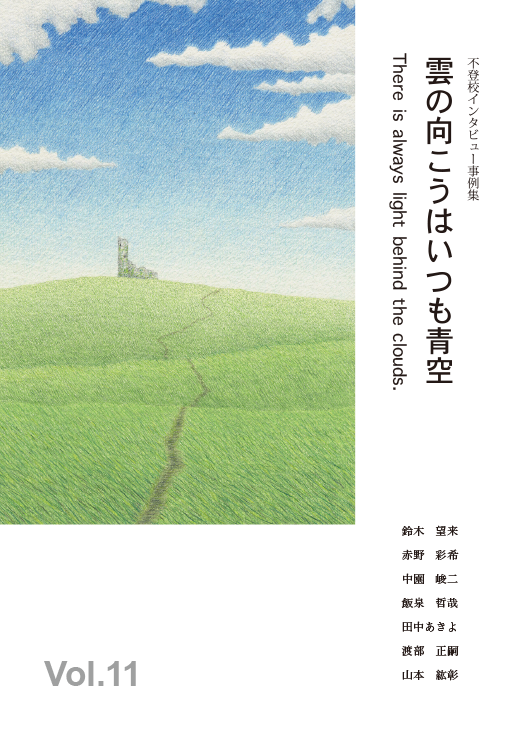










コメントを残す