いや、これはもう、
ぜひみなさんに読んでもらいたい。
そんな本が出た。
今、一気読みして胸が静かに
あたたかくなっている。
『子どもを信じること』の著者、
田中茂樹先生の新刊のことだ。
とかく「子どもを見守る」は
誤解されがちな言葉や態度だと思う。
「見守り教」だの「見守り沼」だの、
揶揄する声も界隈では目にしたりする。
「見守ってればそれで
全部うまくいくんですか?」
そうじゃない。もっと深い話なのだ。
それがとっても胸に響く
タイトルであり、内容だった。
「見守る」とはどういうことか?
「子どもを見守る」とは、放っておくことや無関心であることではありません。あれこれ指示したり、先回りして手を出したりせず、子どもが何に関心を持ち、何を楽しいと思い、何に困っているかに心を寄せる。そして、そばにいる。そのようなかかわり方を、私は「見守る」と呼んでいます。
こう明確に書かれている「見守る」の定義。
それが実に豊富なエピソードで
繰り返し裏付けられていて、
とても腑に落ちるところが多かった。
- 「鼻血では死なない、大丈夫」よりも「怖かったやろうね」
- 決勝戦で負けたのを自分のせいだと責め続ける子に対してどうあるべきか
- 脱ぎ散らかした服を「片づけなさい」と言うのをやめて親が片付けるようになったら起こった、驚きの変化のこと
- 「残念!」と思ったのは親だけだった、スライダープールのエピソード
- 去っていくクライエントの後ろ姿の強さのこと
などなど。
印象的な話に加えて田中先生ご自身の
失敗や反省も含めて書かれている。
とってもよかった。胸がじんわりなった。
この本の目的は明確です。「読んでしんどくならないこと」「子育てが少しでも楽になること」。そして、読んだ方が、「これでいいんだ」と思えるようになることです。
まさに本当にその通りの一冊で!
「これでいいんだ」と僕も心底思えた。
もう子育て世代の方にはもれなく
全員、必ず全部読んでほしい。
なので細かい内容の紹介は
むしろ・あえて・したくない。
「良いからとにかく読んで!」
とだけ言っておく。
はい、みなさん今すぐポチってくださいね。笑
「子どもを見守る」とは、親の思う方向に引っ張らないこと。それでも、子どもは親の背中から、価値観や姿勢をしっかり受け取っていきます。
子どもという、自分とは別の一人の人間が、この時代をどう生きていくのかを模索していく。その姿をそばで見守ること。それこそが、親にできることであり、育児の大きな喜びでもあります。
子どもと過ごす時間は、将来のための「準備期間」ではありません。今この瞬間こそが、人生の目的であり、かけがえのない時間なのだと、私は思います。
将来のための準備期間。
そんなふうに思っちゃってるよね。
無意識に、やっぱり心のどこかで。
本当にそれに気づかされます。
今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!


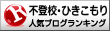

















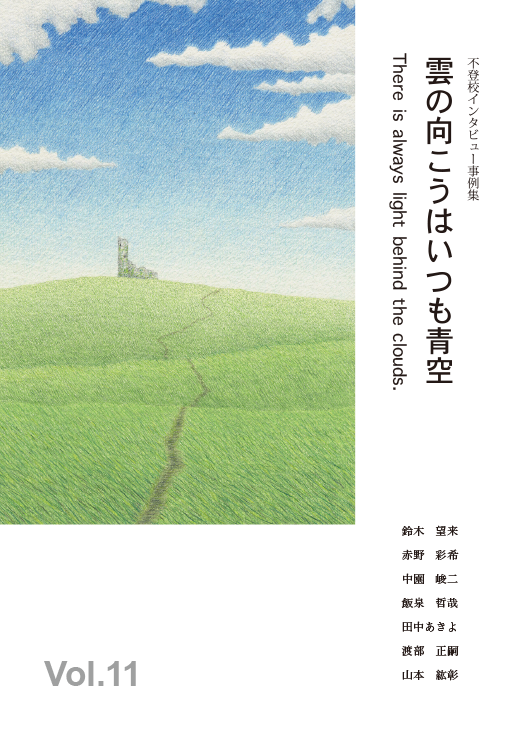










素敵な紹介をありがとうございます。
雲の向こうはいつも青空、やびーんずネットで出していただいた自分の本の文章の感じ、蓑田さんの文章などからも、いろいろ影響を受けていると思います。前より楽に書くようになったような。
今後もよろしくお願いします。
田中先生、コメントありがとうございます!
そんな風に仰っていただけて大変光栄です。今後ともよろしくお願いします。