昨日に引き続いて広木先生の新刊から。
子どもの「心の傷」に最もこたえる
父親の言葉、のくだりが
僕にはめちゃんこ刺さった。
まさに、当時の僕そのものだったかもと。
読んで胸がシクシク痛んだ。
「三学期から頑張って学校行ってみようか」
「行ってみれば行けるんじゃない?」
いや、書いてみて改めて思う。
ふたつめの奴なんてさ、
もはや日本語にさえなってない。笑
ただの自分の願望をぶつけてるだけだ。
でも12年前、息子が不登校になったとき、
一緒にお風呂に入りながら、
そんな励ましをした繰り返した記憶がある。
話を戻す。
親が持ち出す「普通」という
「比較のモノサシ」の言葉の他に――。
不登校の子を持つ親たち、
特に父親には、もう一つ別の
比較のモノサシを持ち出していることが多い
という話だった。
「二人の子どもの比較」
というモノサシだ。
どういうことか?
一人の子どもは目の前の「わが子」。
そしてもう一人の子ども。
それが「子ども時代の自分」だ。
「チャイルド」と「チャイルドフッド」。
この二人の子どもの比較。
それが目の前のわが子を苦しめる。
父親から見れば自分の子ども時代だってつらいことはずいぶんあったと思っています。でもみんなの期待に応えなければと一所懸命頑張り、困難を乗り越え頑張ってくて今の生活がある、と大体そう思っているわけです。ほとんどの大人にとって自分の子ども時代というのは、幾つもあったはずの失敗や逃避の記憶は薄れて語られないのに、困難を乗り越えた成功体験として記憶され、語られている「物語り記憶」なのです。しかし子どもが苦しんでいるときであっても自分の成功体験を基準として語られる父親の話の最後は、一方的な励ましの言葉である「だからお前も頑張れ」で締めくくられることが多いのです。そんな話を聞かされると子どもは自分のすべてが否定されているように感じてしまいます。
「うわあ、これあるわー」
って思いませんか?
少なくとも僕はあった。
だから「このままだとまずい」と焦った。
それなりの大学へ行って、
それなりの会社に入って、
それなりに頑張ってきた。
やっぱりそんな自負があった。
それは、なんのかんの、色々あったけど
つまりは学校へは行ってきたからだ。
そんな自分の子ども時代の
物語があったからこそ――。
将来からの逆算で、今の状態、つまり
「学校に行かないこと」が即、
完全に100%マイナスに結びついた。
だから「頑張って行ってみようか」
と励ました。
でもコレ。
目の前のわが子の否定なんだよね。
頑張れと励ますことが。
この、「親の良かれ」が完全に
子どもに対して逆説として響いていること。
そこに、いかに早く気づけるか。
大切なのはそこなんだよねと。
大事なのは無意識のうちに比べる基準となっている記憶、つまり子ども時代の自分の物語りがあるということです。それを基準として子どもを評価している自分に気づいたら、その比較をできるだけ保留する努力をしてほしいのです。目の前の子どもが、自分にはわからない何かに苦しんでいる、それはいったいどんな苦しみなのかにこそ焦点を当てて考えてみてほしいのです。
それが見えない子どもの「心の傷」に
思いを致すことにつながっていく。
少なくともまず評価する自分に気づいたら
比較を留保する努力をする。
そう、留保する努力。これなんだよね。
本当に多くの人に届いてほしいと思います。
今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。
更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!
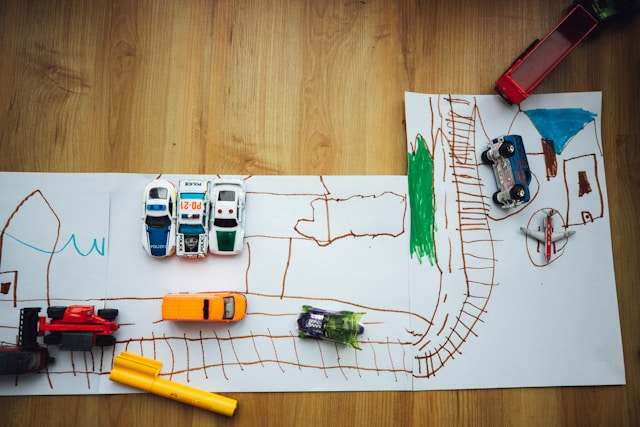

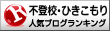











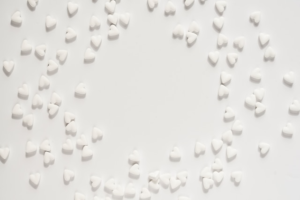





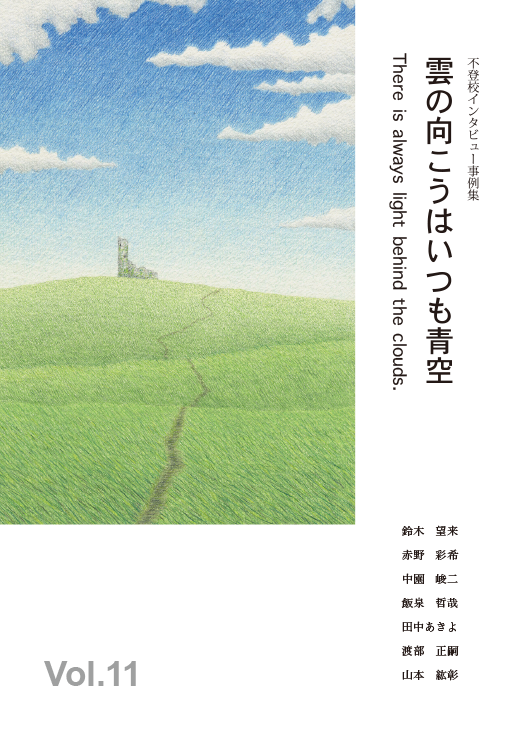










コメントを残す